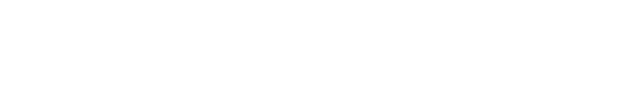糖尿病の薬物療法
糖尿病の薬物療法
― 薬は「コントロールの手助け」。体に合わせて無理なく続けましょう ―
糖尿病は、血糖値が高くなる慢性の病気です。食事療法・運動療法が基本ですが、それだけでは血糖コントロールが難しい場合、**薬物療法(お薬)**が必要になります。
🔸 糖尿病治療薬分類一覧表(作用・特徴・製品名)
| 分類 | 主な作用 | 一般名 | 製品名(例) | 特徴・注意点 |
|---|---|---|---|---|
| ビグアナイド系 | インスリン抵抗性の改善 | メトホルミン | メトグルコ、グリコラン、メトリオン | 胃腸症状あり。体重増加なし。 |
| DPP-4阻害薬 | インクレチンの分解を抑え、インスリン分泌促進 | シタグリプチンリナグリプチンアログリプチンテネリグリプチンアナグリプチンビルダグリプチン | ジャヌビア、トラゼンタ、ネシーナ、テネリア、スイニー、エクア | 低血糖を起こしにくく、使いやすい。 |
| SGLT2阻害薬 | 尿中への糖排泄を促進 | ダパグリフロジンエンパグリフロジンカナグリフロジントホグリフロジンイプラグリフロジン | フォシーガ、ジャディアンス、スーグラ、デベルザ、アプルウェイ | 体重・血圧減少。脱水・尿路感染に注意。 |
| GLP-1受容体作動薬 | インスリン分泌促進、食欲抑制、胃排出遅延 | リラグルチドデュラグルチドセマグルチドリキシセナチドエキセナチド | ビクトーザ、トルリシティ、ウゴービ/オゼンピック、リキスミア、バイエッタ | 体重減少に有効。主に注射製剤。 |
| SU薬(スルホニル尿素薬) | インスリン分泌促進 | グリメピリドグリクラジドグリベンクラミド | アマリール、グリミクロン、オイグルコン/ダオニール | 低血糖リスクあり。慎重な調整が必要。 |
| 速効型インスリン分泌促進薬(グリニド系) | 食直前にインスリン分泌を促す | ナテグリニドミチグリニドレパグリニド | ナテグリニドOD、グルファスト、シュアポスト | 食前に服用。食事を抜くときは服用中止。 |
| α-グルコシダーゼ阻害薬 | 糖の吸収を遅らせる | アカルボースボグリボースミグリトール | グルコバイ、ベイスン、セイブル | 食後高血糖の抑制。腹部膨満感あり。 |
| インスリン製剤 | 血糖を直接下げる | 超速効型:リスプロ、アスパルト、グルリジン中間型・持効型:NPH、デテミル、グラルギン、デグルデク | ヒューマログ、ノボラピッド、アピドラランタス、トレシーバ、レベミル | 注射製剤。きめ細かい血糖調整が可能。 |
📝 備考
-
GLP-1受容体作動薬の**「オゼンピック」は週1回注射型、「ウゴービ」**は肥満治療薬としても使用されます(どちらもセマグルチド)。
-
SGLT2阻害薬の「ジャディアンス」「フォシーガ」は、心不全や慢性腎臓病に対する効果が証明されており、糖尿病以外の適応も注目されています。
-
一部製剤は**配合薬(例:メトホルミン+DPP-4阻害薬)**としても販売されています(例:カナリア、リベルサス、イニシンクなど)。
🔸 各薬剤のくわしい説明
1. ビグアナイド系(メトホルミン)
インスリンの効きを良くする薬です。肝臓での糖の産生を抑え、筋肉での糖の取り込みを助けます。体重が増えにくく、動脈硬化の予防効果も期待されます。
一方で、胃もたれ・下痢などの消化器症状が出ることがあります。
2. DPP-4阻害薬(シタグリプチン、リナグリプチンなど)
インクレチンというホルモンの作用を助け、食後のインスリン分泌を促す薬です。低血糖のリスクが少なく、使いやすい薬剤で、高齢者にも適しています。
食事に関係なく1日1回の内服でよいのも特徴です。
3. SGLT2阻害薬(エンパグリフロジンなど)
腎臓で糖が再吸収されるのを防ぎ、尿と一緒に余分な糖を排出します。血糖値を下げるだけでなく、体重減少や血圧低下にもつながります。
心不全や腎臓の病気がある方にも効果が期待されます。
ただし、脱水や尿路感染症(膀胱炎など)に注意が必要です。
4. GLP-1受容体作動薬(セマグルチドなど)
インクレチンホルモンの働きを強くする薬で、食後のインスリン分泌、胃の動きを遅くする、満腹感を高めるといった作用があります。
体重を減らしたい方に特に有効で、週1回注射で済むタイプもあります。
胃のむかつきや吐き気が出ることがあるため、最初は少量から始めます。
5. スルホニル尿素薬(SU薬)(グリメピリドなど)
膵臓を刺激して、インスリンの分泌を促します。血糖降下作用が強力で、長年使用されてきた薬です。
ただし、低血糖が起こりやすいため、高齢者や腎機能の低下した方には注意が必要です。
6. 速効型インスリン分泌促進薬(ナテグリニドなど)
食事の直前に飲むタイプで、食後血糖値の上昇を抑える薬です。作用時間が短いため、食事を抜いた場合は飲まないようにする必要があります。
7. α-グルコシダーゼ阻害薬(ボグリボースなど)
小腸での糖の分解と吸収を遅らせ、食後の急激な血糖上昇を防ぐ薬です。
野菜を先に食べる「ベジファースト」と相性がよく、食後高血糖を抑えたい方に適しています。
ただし、おならやお腹の張りなどの副作用が出ることがあります。
8. インスリン製剤(超速効型〜持効型)
膵臓から分泌されるホルモン「インスリン」を補う薬です。自己注射で使用しますが、痛みの少ない針やペン型の注射器を使うことで、日常生活への負担を最小限に抑えられます。
食事前に使うものや、1日1回打つだけの長時間型など、複数のタイプがあります。
必要な血糖コントロールに合わせて使い分けます。
🔸 最後に
薬はあくまで「補助的な道具」であり、主役はあなたの生活習慣(食事・運動)です。
糖尿病の治療は、「正しい知識」と「無理のない継続」が何より大切です。
当院では、患者さんの状態やライフスタイルに合わせて最適なお薬を選び、丁寧な説明とフォローアップを行っています。
気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。